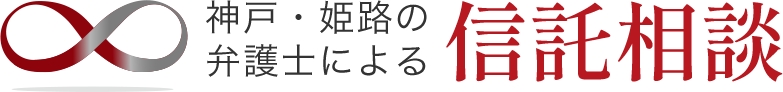解決事例
受託者を予備的に設定することの可否と家族信託を導入する際の注意点について
争点
信託
相談内容
親が高齢になり、最近物忘れも増えてきたため、万が一の場合に備え、家族信託の導入を検討しています。
この場合、私が受託者となって親の財産を管理することになると思うのですが、仮に受託者の方が先に死んでしまった場合や病気等で判断能力を失ってしまった場合、信託契約はどうなるのでしょうか?また、このような事態に備え、受託者を予備的に設定することは可能でしょうか?
加えて、家族信託の導入にあたっては、契約当事者にならない家族にも通知した方がよいのでしょうか?親には私含め子供が3人おり、彼らになにも言わずに信託契約を結んでしまうと、親の財産を隠していると思われたり、事後的に信託契約の無効を主張されたりするのではないかという不安があります。信託を導入する際の事前の注意点を教えていただきたいです。
弁護士の助言・対応
・受託者を予備的に設定することの可否について
信託期間中に、受託者が死亡したり、後見開始の審判を受けたりすると、受託者の任務は自動的に終了するところ(信託法56条1項1号・2号)、新受託者の選任がないまま1年経過すると、信託自体が終了してしまいます(同法163条3号)。そこで、このような場合に信託を継続させるためには、新受託者を選任する必要があります。
この点、信託契約に特に定めがなければ、委託者と受益者の合意により新受託者を選任することになりますが(同法62条1項)、委託者(兼受益者)は高齢な場合が多く、自ら新受託者を選任する意思も能力もない可能性があります。
そこで、信託契約の中で、元々の受託者の任務が終了してしまった場合に備えて、次の受託者を指定しておくことも可能とされています。これを、実務上「後継受託者」と呼びます。今回の場合も、適任者がいる場合には(ご相談者のお子様等)、その方を後継受託者に指定しておき、受託者に何かあった場合でも信託の目的が達成できるようなスキームを組んでおくことが大変重要といえるでしょう。
なお、後継受託者を指定する場合でも、当該後継受託者が、信託契約に立ち会ったり、契約書にサインしたりすることまでは不要です。信託契約の当事者は、あくまでも委託者と元々の受託者であり、信託契約書上も、「○○を後継受託者と指定する」という記載になるため、後継受託者としては、将来、元々の受託者の任務が終了した段階で、次の受託者という地位を引き受けるか否か意思表示すれば足りることになります。
・家族信託を導入する際の注意点について
実務上、委託者(兼受益者)が本当に元気なときに信託契約を締結するというのはあまりなく、今回のように段々と判断能力が落ちてきたタイミングで信託を考えるという方が多いです。そして、信託のことを何も聞かされていない他の家族からすれば、当然いい気持ちにはならないため、信託契約時点で親の判断能力はなかったとして後から無効主張してくるリスクはあると思います。
このような事後的なトラブルを防ぐためには、やはり信託を導入する前に一度家族会議を開いておくのが望ましいです。その際には、信託の当事者となる方から、どういう目的で信託を取り入れるのかしっかり説明し、他の家族の納得・承認を得るという流れで進めるのがよいでしょう。