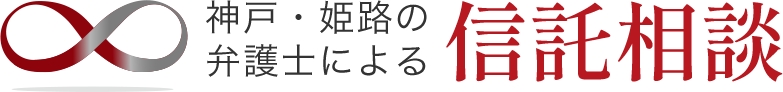コラム
信託終了後に「空き家特例」は使えるの?~東京国税局の見解をもとに~
1 初めに
相続した実家を売却した際の税制優遇措置として知られる「空き家の譲渡所得の3000万円特別控除(空き家特例)」。この特例を利用することで、譲渡所得から最大3000万円控除でき、税負担を大幅に軽減できます。しかし、不動産が信託されていたケースで、信託が終了した後に当該不動産を売却する場合にも、この特例は適用できるのでしょうか。
今回は、この問題について、東京国税局が出した回答をもとに解説いたします。
2 空き家特例とは
⑴ 制度概要
「空き家特例」とは、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋を、一定の要件を満たして売却した場合に、譲渡所得から最大で3,000万円控除できるという制度(租税特別措置法35条3項)です。この制度は、高齢化に伴う空き家問題の解消を目的として、平成28年度税制改正で創設されました。
⑵ 適用要件
空き家特例の適用を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
【建物の要件】
・昭和56年5月31日以前に建築されたこと
・区分所有建物登記がされている建物でないこと(=マンションは適用外)
・相続開始の直前において被相続人以外に居住者がいなかったこと
【売却の要件】
・売主が相続または遺贈により居住用家屋を取得した相続人であること
・相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
・売却価額が1億円以下であること
これらの要件の中で、家族信託と関連して最も重要な論点となるのが、「相続または遺贈により取得した」という部分です。
3 信託の法的構造と所有権の帰属
家族信託は、「委託者」(財産を託す人)が、自身の財産を「受託者」(財産を管理する人)に託し、「受益者」(利益を受け取る人)のために管理・運用・処分を任せる制度です。信託を設定すると、不動産の所有権は形式的には受託者へ移転しますが、これはあくまで信託財産の管理権限を与えるものであり、信託財産から生じた利益は受益者が受け取ることになります。受託者は、自身の固有財産と信託財産を区別して管理しなければなりません。
信託が終了時に残っていた信託財産(=「残余財産」といいます。)は信託契約で定められた「帰属権利者」に帰属します。ここで生じるのが、信託の終了時の残余財産の取得が、空き家特例における「相続または遺贈」に該当するのかどうかという問題です。
4 信託終了後の空き家特例適用の可否~東京国税局の文書回答~
この点について、長らく明確な見解はありませんでしたが、東京国税局は令和4年12月20日付の文書回答で、明確な見解を示しました。それは、信託終了時の残余財産の取得は、「相続または遺贈」に該当せず、帰属権利者が残余財産たる不動産を売却したとしても、空き家特例を適用することはできないというものでした。
その理由について東京国税局は以下の点を挙げています。
①信託終了時の残余財産の取得は、民法上の「相続」または「遺贈」には当たらない。
②相続税法第9条の2は、その実質的な効果から、信託終了時の残余財産の取得を「贈与」または「遺贈」による取得とみなして、贈与税または相続税の課税対象とする旨の規定を置いているが、空き家特例はそのようなみなし規定を置いていない。
③信託行為の当事者ではない帰属権利者は、その権利を自由に放棄することができる(信託法183条3項)。
5 信託を検討する際の留意点
信託の普及とそれに伴う税務上の問題の顕在化により、将来的に税法の改正や、より柔軟な解釈が示される可能性もゼロではありません。しかし、現時点では東京国税局の見解が唯一の公的な判断であり、これに基づいて対策を講じる必要があります。
例えば、以下のような対策が考えられるでしょう。
・将来空き家になる可能性のある不動産については信託財産の対象から除外する。
・信託以外の財産管理・資産承継の方法を検討する(成年後見・遺言等)。
・信託期間中に受託者の権限で売却することで、「居住用不動産を譲渡したときの3000万円特別控除」の適用を受ける。
6 終わりに
東京国税局は、信託終了時の残余財産の取得は、「相続または遺贈」には該当せず、空き家特例を適用することはできないという明確な判断を示しました。これは、信託を利用した不動産の管理において、将来の売却時に税制上の大きな不利益を被る可能性があることを意味します。
家族信託は非常に有用なツールですが、そのメリットとデメリットを十分に理解し、慎重に検討することが不可欠です。今回のような落とし穴にはまらないためにも、信託を導入する段階で専門家にご相談されることを強くおすすめいたします。