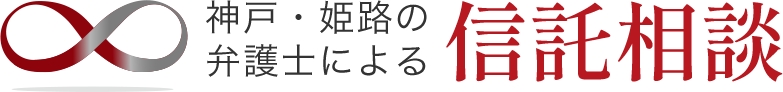コラム
民事信託組成における専門家責任が問われた事例
近年、いわゆる家族信託を利用する例が増加しています。東京地方裁判所令和3年9月17日判決(金判1640号40頁、家庭の法と裁判35号134頁)は、民事信託の組成が適切な方法で行われなかったために、信託組成の目的が達成できなくなるリスクがあること、また、そのような事態が発生した場合に、信託組成に関与した専門家が責任を負う可能性があることを示した裁判例です。本稿では、この裁判例に沿って、民事信託組成時の注意点及び専門家責任について説明します。
1 本裁判例における信託スキーム、請求の経緯
この事例では、委託者兼受益者を父X、受託者を子Aとする信託契約を締結し、委託者Xが所有していた賃貸不動産を受託者Aが管理・処分し、その賃料収入を受益者Xが受け取るという信託スキームが検討されていました。それに加えて、賃貸不動産は、将来的に、大規模修繕が必要となる見込みであったことから、受託者Aは、その際には、賃貸不動産に抵当権を設定して、金融機関から融資を受けることで、この大規模修繕に必要な資金の調達することが予定されていました。
専門家Yは、Xから、この信託組成について依頼を受け、公正証書作成や所有権移転登記等を行いました。しかし、X本人ではなくX代理人YとAの嘱託により信託契約にかかる公正証書を作成してしまったために、金融機関から、信託内融資を受けるための信託口口座を開設することはできないと断られてしまいました。
Xは、このままでは信託の目的が達成できないため、公正証書の作成等をやり直さなくてはならなくなり、これについて、Yに対して損害賠償請求を行いました。
2 信託口口座の開設
本裁判例のように、金融機関から信託口口座の開設や信託内融資を断られないようにするためには、どのようなことに留意すべきだったのでしょうか。
まず、信託口口座の開設の際に求められる条件は金融機関によって異なりますので、事前に金融機関に対して問い合わせを行うことが最も重要です。
信託口口座の開設の際に金融機関から求められる条件は、大別すると、①専門家が関与していること、②当該金融機関から契約条項に関して事前に確認を受けること、③信託契約が公正証書により締結されていることの3点が多く見受けられます。
特に、③公正証書の作成は、公証人により、当事者の信託設定の意思の存在、意思能力が確かなものであることが保証されているといえるため、金融機関としては、重要視することが多いものと考えられます。
3 信託内融資
信託内融資とは、委託者ではなく、受託者が、信託財産責任負担債務(受託者が信託財産に属する財産をもって履行する責任を負う債務(信託法2条9項))として、金融機関から融資を受けることをいいます。
信託内融資については、そもそも、対応している金融機関が限られているため、金融機関に対し、信託内融資に対応しているか否かについて、事前に確認することが重要です。
また、信託内融資を受ける際に求められる条件も金融機関によって異なります。大別すると、①信託契約上、信託内融資の権限が明示されていること、②信託口口座を開設していること、③信託契約に特定の条項を設けることの3点が多く見受けられます。
金融機関としては、融資金債権が回収できないような事態とならないように、各種の条件を求めているものと考えられます。すなわち、②信託口口座の開設の開設が求められる理由は、信託財産である預金債権と融資金債権について、相殺可能性を確保しておくことにあります。また、③金融機関は、信託契約において、信託契約の終了または変更について金融機関の同意を得なければならない条項、信託契約の終了時に帰属権利者が信託内融資を引き受ける条項等を設けることを条件とすることがあります。
4 専門家の責任
信託組成の目的が達成できないような事態が生じた場合、信託組成に関与した専門家は、委任契約の債務不履行に基づく損害賠償責任や不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合があります。
本裁判例では、具体的な事実関係に鑑み、委任契約の債務不履行に基づく損害賠償責任は認められませんでした。ただし、裁判所は、委任契約上専門家が負うべき義務のうち、委託者本人に公正証書作成の嘱託をさせるべき注意義務については、本裁判例当時は、民事信託に関する知見が十分に普及していなかったと考えられることを理由に、Yがそのような注意義務を一般的に負っていたとはいえないと判断しています。そのため、民事信託の活用事例が増加している現在においては、このような一般的な注意義務が認められる可能性があるがあることには注意が必要です。
他方、本裁判例では、YのXに対する不法行為に基づく損害賠償責任が認められました。ここで重要なのは、専門家は、相談や依頼を検討している者に対し、委任契約を締結するに先立ち、信義則に基づき、各種の情報収集や調査を行い、その情報提供を行う義務、また、信託契約締結に際して存在するリスクについて説明する義務を負っていると判断されている点です。
5 まとめ
このように、民事信託を活用しようとする場合には、信託契約の締結前から注意すべき点が多くありますので、民事信託に詳しい弁護士等の専門家に相談することが重要です。当事務所では、民事信託に関するご相談、ご依頼も多数取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。